子育てをしている皆さんは、毎日何気なく子どもにかけている言葉が、実は子どもの人生に深い影響を与えていることをご存じでしょうか。犯罪心理学者の出口安之氏は、少年鑑別所や刑務所で約1万人もの非行少年を心理分析してきた経験から、衝撃的な事実を明らかにしています。それは、非行少年の多くが「1人で勝手に悪化した」のではなく、大人たちの言葉や関わり方の犠牲者であるということです。
日常の何気ない言葉かけや、良かれと思って伝えている価値観の押し付けが、子どもにとっては呪いのように機能し、思わぬ方向へ導いてしまうケースが少なくありません。この記事では、出口氏が指摘する「呪いの言葉」のランキングと、それぞれの言葉が子どもに与える具体的な影響、そして何より重要な「救いの言葉」への変換方法をご紹介します。
親であるあなたの言葉を少し変えるだけで、子どもの未来は大きく変わる可能性があります。この記事を通して、親子関係をより良いものにするヒントを見つけていただければ幸いです。
第5位:「みんなと仲良くしなさい」が子どもを追い詰める理由
なぜこの言葉が問題なのか
「みんなと仲良くしなさい」という言葉は、一見すると協調性を育てる良い言葉のように聞こえます。しかし、この言葉を繰り返し言われ続けた子どもの中には、深刻な問題を抱えるケースがあることが分かっています。
ある事例では、親が協調性を最優先し、子どもの本音を聞かずに「みんなと仲良くしなさい」と強要し続けた結果、子どもは親に本音を言わなくなってしまいました。表面上は親の言いつけを守っているように見えましたが、実際には本音を聞いてくれる万引癖のある友人と親密になり、最終的には万引グループに入って窃盗で逮捕されるという結果になりました。
問題の本質
「みんなと仲良く」という要求は、実は綺麗ごとに過ぎません。社会には様々な価値観や立場の違いがあり、全ての人と仲良くすることは現実的に不可能です。この言葉を押し付けられた子どもは、自分の感情や価値観を押し殺し、無理に周囲に合わせようとします。その結果、本当の自分を理解してもらえないという孤独感や、親に対する不信感を募らせていくのです。
子どもが苦手な人や合わない人がいることは、むしろ自然で健全なことです。大切なのは、無理に仲良くすることではなく、苦手な人との適切な距離の取り方を学ぶことなのです。
実践的な対処法:子どもに教えるべき3つの距離の取り方
子どもが実際に実行できる具体的な方法として、以下の3つのアプローチがあります。
まず第一に、家のルールを理由にする方法です。気乗りしない誘いを受けたとき、子どもは「うちの家ではそれができないんだ」と伝えることができます。これは親のルールを言い訳にすることで、子ども自身が責任を負わずに断ることができる有効な方法です。親は子どもがこの言い訳を使うことを事前に承認し、サポートする姿勢を示すことが大切です。
第二に、物理的に距離を取る方法があります。トイレに行く、忘れ物を取りに行く、保健室に行くなど、適当な理由をつけて物理的な距離を作ることで、苦手な相手との関わりを最小限にする技術を身につけることができます。これは社会人になってからも使える重要なスキルです。
第三に、自分の世界を持つことです。帰宅後にできる好きな活動、例えばゲーム、ペットの世話、趣味などを持つことで、無理に苦手な相手と交わらずに済む環境を作ることができます。自分だけの安全な場所や時間があることは、子どもの精神的な安定にとって非常に重要です。
第4位:「早くしなさい」が先を読む力を奪う
急かすことの弊害
「早くしなさい」という言葉は、忙しい朝や時間に追われている時につい口にしてしまう言葉です。しかし、この言葉を常に浴びせられて育った子どもには、深刻な問題が生じることがあります。
ある事例では、父親から常に急かされることで、子どもは将来の目標や夢を持たず、その場しのぎの思考パターンに陥ってしまいました。結果として、大人になってから業務上横領などの短絡的な犯罪に手を染めてしまったケースが報告されています。
なぜ「早く」だけでは効果がないのか
子どもは発達段階において、先を読む力がまだ十分に育っていません。単に「早くしなさい」と急かすだけでは、子どもは「なぜ急ぐ必要があるのか」「急がないとどうなるのか」という因果関係を理解できないのです。理由も分からず急かされ続けることで、子どもは目の前のことだけに対処する思考パターンが固定化してしまいます。
時間感覚と先を読む力を育てる実践的アプローチ
親の役割は、急ぐ理由を丁寧に説明し、子ども自身に考えさせることで、時間感覚や先を読む力を育てるトレーニングをすることです。例えば、「あと15分で家を出ないと、電車に乗り遅れて学校に遅刻してしまうよ。そうすると先生や友達に迷惑をかけることになるね」というように、時間と結果の関係性を具体的に示すことが重要です。
また、忙しい時の現実的な対応策として、親が先回りして「急がなくても済む仕組み」を作る工夫も効果的です。朝の支度計画を前日に一緒に立てる、目に見える位置に時計を設置する、準備物を前日の夜に揃えておくなど、子どもが自分で時間管理しやすい環境を整えることで、親の負担も減り、子どもの自律も促すことができます。
学習面においても、例えば読むのが遅い子に対して「早く読め」と言うだけでは改善しません。語彙力を増やす、効率的な読書法を教える、トレーニング方法を示してチェック体制を組むといった教育的対応が必要なのです。
第3位:「何度言ったら分かるの」が自己肯定感を破壊する
繰り返しの叱責が生み出す負のスパイラル
母親が何度も同じことで激怒し、「何度言わせるの」「いい加減にしなさい」と繰り返すことで、子どもは「何度言ってもダメな自分」という否定的な自己イメージを内面化してしまいます。この事例では、子どもの自己肯定感が著しく低下し、青年期に深刻な問題行動につながったケースが報告されています。
青年期前に自己肯定感を育てる重要性
青年期、つまり13歳から25歳の時期は、心身の急速な発達と同時に強い不安が生じる時期です。この時期を健全に乗り越えるためには、それ以前に十分な自己肯定感を育てておくことが極めて重要になります。自己肯定感が低いまま青年期を迎えると、ストレスに対する耐性が弱く、様々な問題行動のリスクが高まります。
無条件の愛情を言葉で伝える
親は子どもに対して、「あなたが元気でいてくれるだけで嬉しい」といった無条件の肯定メッセージを繰り返し伝えることが必要です。これは単なる甘やかしではありません。比較や成果に基づく評価ではなく、「そのままのあなたを大切に思っている」という言葉を意識的に使うことが、子どもの自己肯定感の土台を作ります。
受験や成績の話題で感情的になりそうな場面では、まず子どもの気持ちを受け止めてから、他の選択肢を一緒に考える姿勢が大切です。否定から入るのではなく、伴走する姿勢を示すことで、子どもは「失敗しても親は自分の味方でいてくれる」という安心感を得ることができます。
教育者や塾講師の立場でも同様です。怒鳴る代わりに「心のゆとり」を持って接する工夫や、生徒が聞きたくなる言葉遣いの訓練を行う必要があります。プロとしての姿勢は、どれだけ相手の心に届く言葉を選べるかにかかっているのです。
第2位:「勉強しなさい」が引き起こす予想外の反発
強制が生み出す極端なケース
「勉強しなさい」という言葉は、多くの家庭で日常的に使われています。しかし、この言葉を執拗に強制され続けた結果、家族に暴力を振るうなど極端な犯罪に至ったケースや、入試のプレッシャーで他者を巻き込む事件につながった事例が報告されています。
青年期のストレスと視野狭窄
青年期に強いストレスを受け続けると、心理的視野が極端に狭くなります。この状態では、物事を冷静に判断する能力が低下し、社会に対する怒りや過激な行動に走る危険性が高まります。特に勉強に関する強制は、将来への希望を奪い、「今すぐこの苦痛から逃れたい」という短絡的な思考を生み出します。
勉強への動機づけを変える具体的方法
「勉強しなさい」と言う代わりに、まず勉強の面白さを伝えることが重要です。学習内容を子どもの興味に結びつける工夫をすることで、勉強は「やらされるもの」から「やりたいもの」に変わります。例えば、歴史が好きな子には歴史的背景を絡めて数学の問題を説明する、ゲームが好きな子にはゲーム理論と結びつけて論理的思考を教えるなどの工夫が考えられます。
また、目標をスモールステップに分けて達成感を積ませる手法も効果的です。大きな目標をいくつかの小さな目標に分解し、一つ一つクリアする喜びを経験させることで、自然と学習意欲が高まります。ただし、この方法が合わない子もいます。勉強を嫌う子にはスモールステップが逆効果になることもあるため、その場合は楽しく学べる工夫が必要です。
具体的には、内容を好きなことに結びつける、ゲーム化する、大げさに面白く説明するといった娯楽性を導入することが有効です。受験指導者の実践例として、授業をエンターテインメント化する工夫も紹介されています。学習内容を日常の具体例に結びつける、答えを与えずに考えさせるヒントを出す、誇張して面白く伝えるといった方法は、プロの教育者だけでなく、家庭でも応用できるテクニックです。
第1位:「頑張って」が子どもを追い詰める意外な真実
励ましのはずの言葉がなぜ呪いになるのか
「頑張って」という言葉は、一般的には応援や励ましの言葉として広く使われています。しかし、犯罪心理学の専門家によれば、この言葉が最も危険な「呪いの言葉」の第1位に位置づけられています。その理由は何でしょうか。
被害感や阻害感が強い子どもにとって、「頑張って」という言葉は「頑張れないお前はダメだ」という否定的なメッセージとして受け取られる場合があります。既に十分頑張っている子ども、あるいは頑張ることに疲れ果てている子どもに対して「頑張って」と言うことは、さらなるプレッシャーを与え、「まだ足りないのか」という絶望感を生み出します。
言葉より関係性が重要
重要なのは、言葉そのものよりも日頃の親子関係です。親が本当に子どもを大事に思っているというメッセージが日常的に伝わっていれば、「頑張って」という言葉も素直な励ましとして受け取られます。しかし、関係性が良くない状態で同じ言葉を使うと、逆効果になり得るのです。
つまり、どんなに良い言葉を選んでも、親子の信頼関係が築けていなければ、その言葉は子どもの心に届かないばかりか、かえって傷つけてしまう可能性があるということです。
頑張る才能がない子への別のアプローチ
「頑張る」こと自体を良しとする価値観は、実は全ての人に当てはまるわけではありません。頑張る才能がない子や、頑張ることが苦手な子も確実に存在します。そうした子どもたちに対しては、無理に頑張らせるのではなく、楽しめる方法を一緒に探るアプローチが必要です。
具体的には、工夫や工夫のプロセスを褒める、小さな進歩を認める、結果よりも取り組み方を評価するといった方法があります。「頑張って」の代わりに、「面白いやり方を見つけたね」「自分なりの方法を工夫したね」「楽しそうに取り組んでいるね」といった言葉を使うことで、子どもは自分のペースで成長していくことができます。
親子関係を支える実践的な仕組みづくり
環境整備で子どもの自律を促す
言葉かけを改善することと同時に、子どもが自然と適切な行動を取れるような環境を整えることも重要です。朝の支度がスムーズにできるように準備物の定位置を決める、時間が見えるように時計を配置する、学習環境を整えるといった物理的な工夫は、親の負担を減らすと同時に、子どもの自律性を育てることにつながります。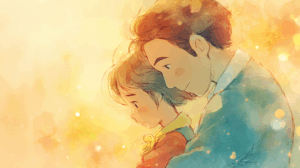
継続的な学びの場の活用
親自身が学び続けることも大切です。受験指導者が運営する会員制サービスやイベント、例えば受験YouTuberフェスタなどに参加することで、他の保護者と情報交換したり、専門家からアドバイスを受けたりすることができます。保護者向けの動画教材を活用して、具体的な声かけや学習法を学ぶことも有効です。
長期的視点を持つことの重要性
子育ては短距離走ではなくマラソンです。短期的な成果に焦らず、長期的な視点で子どもの成長を見守ることが大切です。肩の力を抜いて、子どもの個性や成長のペースを尊重する姿勢が、結果的に子どもの健全な発達を促します。
必要であれば、専門家、教育イベント、教材などの外部リソースを積極的に活用することをためらう必要はありません。一人で抱え込まず、様々なサポートを受けながら子育てをすることは、賢明な選択です。
さらに深く学びたい方へ:出口保行氏の書籍のご紹介
この記事でご紹介した内容は、犯罪心理学者である出口保行氏の書籍「犯罪心理学が教えるこどもを呪う言葉・救う言葉」を元にしています。出口氏は少年鑑別所や刑務所で約1万人もの非行少年を心理分析してきた経験を持ち、その豊富な実践経験から得られた知見が本書には凝縮されています。
この書籍から学べること
本書では、この記事で紹介した5つの「呪いの言葉」についてさらに詳細な事例と分析が記載されています。それぞれの言葉がなぜ子どもを追い詰めるのか、どのような心理的メカニズムが働いているのかについて、犯罪心理学の専門的な視点から深く掘り下げられています。
また、単に問題点を指摘するだけでなく、具体的な「救う言葉」への変換方法や、日常生活で実践できる声かけの技術が豊富に紹介されています。実際の非行少年たちとの面談を通じて得られた生の声や、彼らが親に本当に求めていたことなど、現場でしか知り得ない貴重な情報が満載です。
こんな方におすすめです
子育て中の親御さんで、日々の言葉かけに悩んでいる方には特におすすめです。良かれと思って使っている言葉が実は子どもを傷つけているかもしれないという不安を抱えている方、子どもとのコミュニケーションをより良いものにしたいと考えている方にとって、本書は具体的な指針を与えてくれます。
また、教育関係者の方々、例えば学校の先生、塾講師、習い事の指導者の方々にも大変参考になる内容です。日々子どもたちと接する中で、どのような言葉をかければ子どもたちの可能性を引き出せるのか、逆にどのような言葉が子どもたちの成長を妨げるのかを、科学的な裏付けとともに学ぶことができます。
さらに、祖父母の方々や、子どもに関わる全ての大人の方々にもお読みいただきたい一冊です。世代による子育ての価値観の違いを理解し、現代の子どもたちに適切な関わり方を学ぶことができます。
書籍の特徴と実践的価値
本書の最大の特徴は、理論だけでなく実践に重きを置いている点です。犯罪心理学という専門分野の知見を、誰でも今日から実践できる具体的なアクションに落とし込んでいます。難しい専門用語は最小限に抑えられ、読みやすく分かりやすい文章で書かれているため、心理学の知識がない方でもすぐに理解し、実践することができます。
また、本書で紹介されている事例は、極端な犯罪事例だけでなく、一般的な家庭でも起こり得る身近な問題も多く含まれています。そのため、「うちの子は大丈夫」と考えている方にこそ読んでいただきたい内容となっています。予防の観点から、今のうちに適切な言葉かけを身につけることで、将来の深刻な問題を未然に防ぐことができるのです。
詳しい情報と購入方法
書籍「犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉」は、全国の書店やオンライン書店でお求めいただけます。
【書籍情報】
- タイトル:犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉(SB新書)
- 著者:出口保行
- 出版社:SBクリエイティブ
- 発売日:2022年8月9日
- ページ数:224ページ
- ISBN-13:978-4815616533
Amazonで購入する
また、よりわかりやすいマンガ版も発売されています。文章を読むのが苦手な方や、視覚的に理解したい方にはこちらもおすすめです。
YouTube動画でも学べます
出口保行氏の解説動画もYouTubeで公開されており、書籍と合わせてご覧いただくことで、より深い理解が得られます。この記事の元となった動画は以下のリンクからご覧いただけます。出口氏本人による解説を聞くことで、文章だけでは伝わりにくい細かなニュアンスや、実際の現場での経験談などを知ることができます。
関連動画:https://youtu.be/SDgupXDCxH0?si=y7FsEVoyCUQh-qNR
動画では受験指導者との対談形式で進められており、犯罪心理学の専門家の視点と教育現場の実践者の視点の両方から、子どもへの言葉かけについて深く掘り下げられています。この二つの視点の融合により、理論と実践がバランスよく学べる内容となっています。
今すぐ始められる第一歩
子どもの未来を変える第一歩は、親であるあなた自身が学び、変わることから始まります。本書を手に取り、今日から実践できる具体的な方法を学んでみてはいかがでしょうか。あなたの言葉が変われば、子どもの未来も変わります。
書籍で深く学び、動画で実践的なニュアンスを理解し、そして日常の中で少しずつ実践していく。この三つのステップで、あなたの子育ては確実に変わっていきます。まずは書籍を手に取ることから始めてみませんか。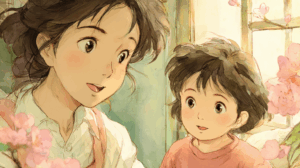
まとめ:言葉を変えることは関係性を変えること
同じ言葉でも関係性次第で意味が変わる
この記事で紹介した「呪いの言葉」のランキングから分かることは、言葉そのものの問題というよりも、その言葉が使われる文脈や親子関係の質が重要だということです。同じ言葉でも、親子関係や子どもの心理状態によって、救いの言葉にも呪いの言葉にも変わり得るのです。
日常の信頼関係作りが最優先
したがって、最も重要なのは日常的な信頼関係を築くことです。親は言葉を変えるだけでなく、子どもの受け取り方に配慮し、日々の関係の質を高める行動を心がける必要があります。具体的には、無条件の肯定を示す、説明して考えさせる機会を作る、楽しさを共有するといった姿勢が大切です。
今日から実践できる3つのポイント
第一に、子どもの苦手な対人関係への対処法を一緒に考えることです。無理に「みんなと仲良く」を強要するのではなく、適切な距離の取り方を教えることで、子どもは社会で生きる知恵を身につけます。
第二に、時間管理や先を読む力を育てる仕組みを作ることです。「早くしなさい」と急かすのではなく、なぜ急ぐのかを説明し、自分で時間管理できる環境を整えることで、子どもの計画性が育ちます。
第三に、自己肯定感を高める言葉かけを実践することです。「何度言ったら分かるの」「勉強しなさい」「頑張って」といった言葉を控え、代わりに無条件の愛情や具体的な認知の言葉を使うことで、子どもは心の安定を得ることができます。
完璧な親である必要はない
最後に大切なことは、親は完璧である必要はないということです。時には感情的になってしまうこともあるでしょう。大切なのは、自分の言動を振り返り、少しずつ改善していく姿勢です。子どもは親の完璧さを求めているのではなく、自分を大切に思ってくれる気持ちや、一緒に成長しようとする姿勢を求めているのです。
親の言葉を変えることは、子どもの未来を変えることにつながります。今日からできる小さな一歩を踏み出すことで、親子関係はより良いものになっていくはずです。この記事が、あなたと子どもの関係をより豊かなものにするきっかけになれば幸いです。
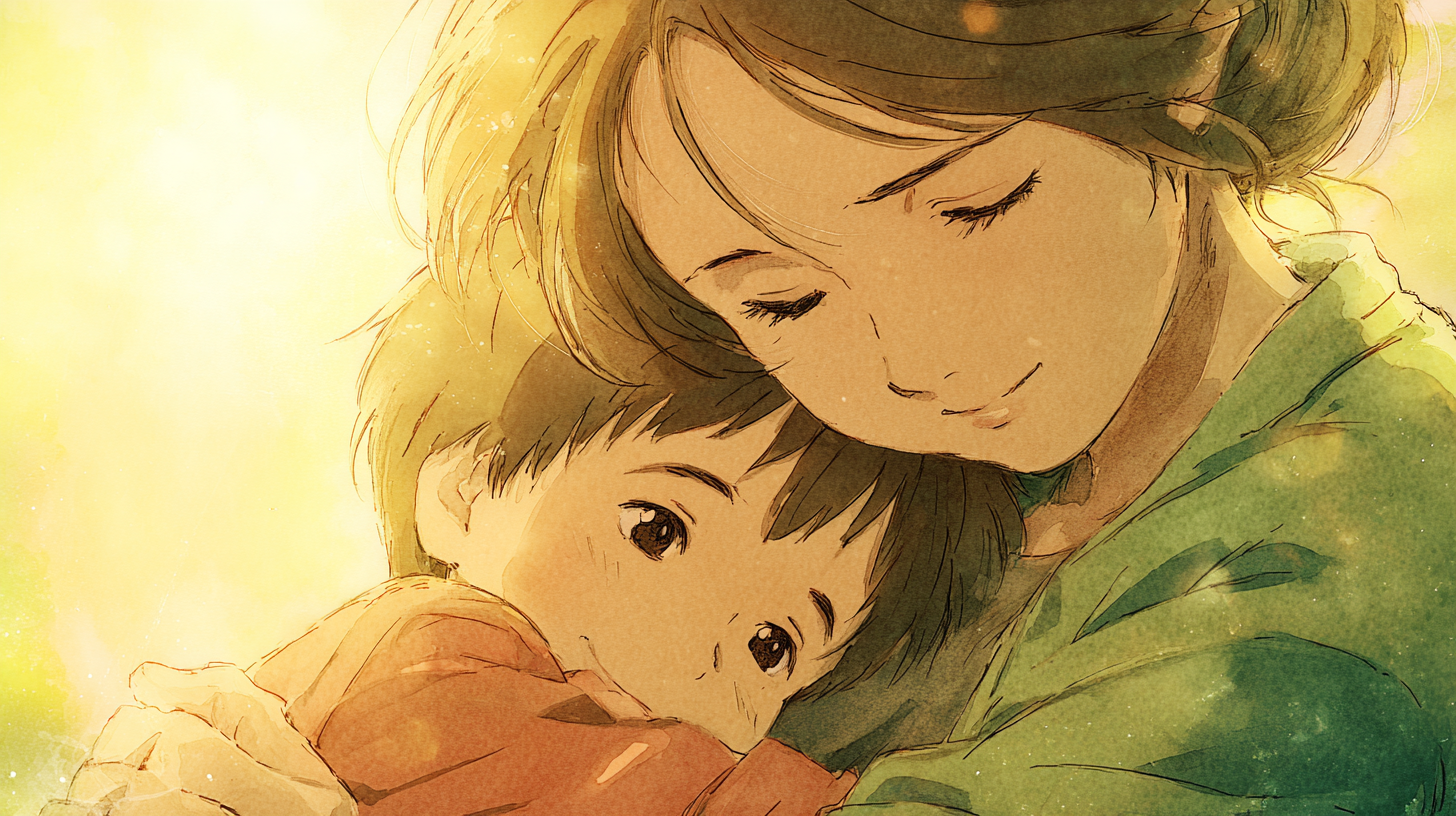
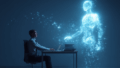
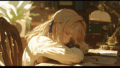
コメント